そして、約束の日から2日後。 外は相変わらずの雨模様だった。
私たちが『霧笛のティーハウス』のカウンターで、重苦しい沈黙に包まれながら紅茶を飲んでいた、その時だった。
ジリリリリリ……!!
店内の静寂を切り裂くように、カウンターの固定電話が鳴り響いた。その甲高い音に、私たちはびくりと肩を震わせた。 煌良ちゃんが、震える手で受話器を取る。
「……はい、ロイヤル・リーフです」 「……はい、お父さん? ……え? うそ……嘘よ……」
カウンターの中で電話を受けた煌良ちゃんの顔から、さっきまでの血色が嘘のように引いていく。震える手で受話器を握りしめる彼女を見て、私と姉は顔を見合わせた。姉が読んでいた本を静かに閉じる音が、不吉な合図のように響いた。
電話の相手は、煌良ちゃんの父親であり、警視庁の刑事である本多景忠さんだった。彼は沈痛な声で、娘にこう告げたという。
「……身元不明の遺体が出た。確認に来てほしい」
外に出ると、雨は小降りになっていたが、空気は湿り気を帯びて重く、私たちの足取りにまとわりついた。 久世さんが行方不明になったあの日から、何かあった時のためだろう、姉はずっと煌良ちゃんの店の駐車場に愛車を停めていた。「即応体制(スタンバイ)よ」と姉は言っていたけれど、その準備がこんな形で使われることになるなんて。
私たちは、雨に濡れた真っ赤な車に乗り込み、文京区大塚にある東京都監察医務院へと急いだ。
地下にある霊安室(遺体確認室)。 分厚い鉄の扉が開かれた瞬間、鼻をついたのは、消毒液の鋭い刺激臭と、どこか湿った鉄が錆びたような、独特の臭いだった。 それは「終わってしまった命」の臭いだ。
空調の低い唸りだけが響く、無機質な空間。 部屋の中央にはストレッチャーが置かれ、その上には残酷なほど平坦な白布が掛けられている。その下にある膨らみが「人」の形をしていることが、どうしようもなく恐ろしい。
「……酷なことを頼んですまない、煌良」
本多刑事が、苦渋に満ちた顔で娘の肩を抱いた。 普段は「人情派」として知られ、柔和な笑顔を絶やさない彼にとっても、娘を親友のなきがらの前に立たせることは、身を切られるような辛さなのだろう。 煌良ちゃんは、白布を見つめたまま動けない。指先が震え、唇が何かを言おうとして引きつっている。
「お父さん……どうして、美月だってわかったの?」 「……昨夜の豪雨で、多摩の山中で大規模な土砂崩れがあったんだ。そこから複数の遺体が見つかった。その中の一体が……お前が相談してくれた、久世美月さんの特徴と似ていたんだ」
本多刑事の声が僅かに震える。彼は、強張った顔でその経緯を語り始めた。
「発生は、昨夜の22時過ぎだ。ここ数日降り続いた長雨のせいで地盤が緩み、斜面が崩落した。幸い、近くに民家はなく、巻き込まれた住民はいなかった。死者も負傷者もゼロ……そう思われていた」
本多刑事は、悔しそうに拳を握りしめた。
「だが、周辺を捜索していたレスキュー隊員が、土砂の中に埋もれている『人のような影』を見つけたんだ。隊員は生存者だと思って声をかけ、泥まみれになりながら引き上げた。……しかし、そこにあったのは、助けを求める人間ではなかった。土砂崩れで亡くなったにしては不自然すぎる……無残な姿を晒した遺体だったんだ」
私の背筋に冷たいものが走る。 災害現場から見つかったのに、災害の犠牲者ではない。それは、何者かによって「捨てられた」ということだ。
「現場の判断で、直ちに警察へ連絡が入った。所轄署が丹念に周辺の土砂をさらった結果……そこから出てきたのは、一体だけじゃなかった。白骨化したものを含め、複数の遺体が、まるで地層のように埋まっていたんだ」
「……それで、警視庁(ほんちょう)にお鉢が回ってきたのね」
姉が静かに言葉を継いだ。 単なる変死体遺棄ではない。連続性のある異常犯罪。所轄の手に負える規模ではない。
「ああ。日付が変わる頃に捜査一課へ連絡が入り、警視庁管轄の重要事件となった。俺も夜中に叩き起こされて、現場へ走ったよ」
本多刑事の目には、徹夜明けの疲労と、それ以上に深い憤りが滲んでいた。
「服装、髪型、背格好……ただの刑事の勘だと思いたかったが……」
本多刑事はそこで言葉を切り、沈痛な面持ちで懐から透明な証拠品袋を取り出した。
「……まずは、これを見てくれ。遺体が身につけていた遺留品だ」
差し出された袋の中には、泥にまみれ、黒ずんだ銀色のペンダントが入っていた。鎖は無残にちぎれ、トップの飾りもひしゃげているが、その特徴的な意匠は見て取れた。 煌良ちゃんが、ハッと息を呑む。 大きな瞳が揺れ、みるみるうちに涙の膜が張っていくのがわかった。
「……これ」 「見覚えがあるか?」
父親の静かな問いに、煌良ちゃんは震える声で答えた。
「……似てる。私が、美月の誕生日にあげたものに……すごく、似てる」
けれど、次の瞬間、彼女は強く首を横に振った。拒絶するように。
「でも、違う! こんなデザイン、どこにでもあるわ! 既製品だもの、同じものなんて世の中にいくらでもある! だから……これだけで美月だって決まったわけじゃない!」
それは、祈りにも似た悲痛な叫びだった。 当然だ。認めたくない。否定したい。 誰よりも優しくて、大切だった親友が殺されて、こんな冷たい場所で変わり果てた姿になっているなんて、あってはならないことだ。
あの子は生きている。今もどこかで生きていて、ひょっこり帰ってくるはずだ。そう信じたい。 この期に及んでもなお、死という絶望的な現実を受け入れたくないという彼女の心が、痛いほど私の中に流れ込んでくる。その拒絶の強さが、共感能力者(エンパス)である私の胸をきりきりと締め付けた。
「おい、本多さんよ」
突然、本多刑事の言葉を遮るように、ドスの効いた低い声が響いた。 部屋の奥、暗がりに立っていた男が、ゆっくりとこちらへ歩み寄ってくる。 鋭い眼光を放つ中年男性。 着古したスーツ、無精髭、そして全身から発せられる「拒絶」のオーラ。 警視庁捜査一課、宗像亮治(むなかた りょうじ)警部だ。
「いくら身元確認とはいえ、部外者をゾロゾロ連れ込むな。特に……」
宗像警部の、敵意に満ちた視線が姉・佳穂に向けられる。
「なんで民間人の、しかも小娘がここにいる」
姉は動じない。宗像警部の威圧的な態度を、まるで道端の石を見るような無関心な瞳で見返している。 一触即発の空気。 その時、カツカツという硬質なヒールの音が、冷たい床を叩いた。
「彼女たちは参考人です、宗像警部」
凛とした声と共に現れたのは、完璧に仕立てられたパンツスーツを着こなした、知的な美女だった。 水谷川芽瑠(みやがわ める)警視。
身長は158cmと小柄だが、その背筋は鋼が入ったように伸びており、周囲を圧するような強烈なオーラを放っている。 特徴的なのは、その髪だ。膝の裏まで届く、艶やかな長い黒髪。今は仕事中ゆえに高い位置でポニーテールに束ねられているが、歩くたびに流麗な軌跡を描き、彼女の「特別性」を無言のうちに主張している。
今でこそ、こうしてキャリア組の警視として氷のような威厳を放っているけれど、その美しい仮面の下には、実はかなりの「ちゃめっ気」と「好奇心」を隠し持っている人だ。 姉の高校時代の先輩であり、現在は警視庁殺人犯捜査係の係長を務める人物。 そして――この世で唯一、あの「魔王」と呼ばれる姉・佳穂に、完全な敗北を味わわせた相手でもある。
姉は、頭脳だけでなく武道においても天才だ。 中学・高校時代と空手道場に通い、そこには後に「科学の天才」となる九条芙美音(くじょう ふみね)という相当な猛者の同級生もいたのだが、姉は彼女にすら勝ち越していた。高校生が出場するような大会でも負け知らずで、まさに無双状態だったのだ。
そんな姉が高校に入り、なぜか入部した「心霊倶楽部」。 そこで部長として君臨していたのが、当時3年生の水谷川芽瑠だった。 芽瑠先輩はいわゆる「秀才」だ。佳穂のような突飛な天才性とは違う、積み上げられた努力と、他者を牽引する圧倒的な「統率力(カリスマ)」の持ち主。
実は先輩、空手部にも所属していたらしい。新入部員の佳穂が空手の有段者だと知るや、ニヤリと不敵に笑って「手合わせ」を申し込んだという。 結果は――姉の、人生初の完敗。 姉曰く、「悔しいという感情すら湧かなかった」そうだ。 それほどまでに、芽瑠先輩の強さは圧倒的で、次元が違っていたらしい。技のキレ、スピード、そして何より「絶対に勝つ」という精神的圧力(プレッシャー)。
その後、芽瑠先輩は、姉と、同じく心霊倶楽部に入っていた芙美音ちゃんの二人を強引に誘い、空手の大会に出場した。 大将・芽瑠、中堅・佳穂、先鋒・芙美音。 『芽瑠・佳穂・芙美音』。 この規格外の三人が揃ったチームは、他を寄せ付けない圧倒的な強さで、すんなりと団体優勝を奪い去った伝説を持っている。
そんな「最強の先輩」だが、彼女には一つだけ奇妙な点があった。 生徒会長を務めるほどの優等生でありながら、「不思議なこと」が大好きだったのだ。 幽霊、UFO、怪奇現象。
『この世には、私たちの論理じゃ測れないナニカがあるのよ。ワクワクしない?』
そう言って目を輝かせる彼女にとって、IQ240の頭脳を持つ佳穂や、マッドサイエンティストの芙美音といった「規格外の後輩たち」は、格好の観察対象であり、愛すべき仲間だったのだろう。
そんな、頭が上がらない「女帝」を前にしては、今の姉も少しだけ神妙な顔つきになる。
「芽瑠先輩」
姉が小さく呟く。
「久しぶりね、佳穂。……帰国早々、こんな場所で会うことになるとは思わなかったけど」
水谷川警視は短く挨拶を交わした。 その瞳には、かつての「戦友」であり、可愛い後輩である姉に対する信頼と、現状への厳しい認識が宿っている。 彼女は姉が英国にいる間も、警察組織の壁にぶつかるたびにこっそりと連絡を取り、何度も難事件のプロファイリングを依頼していたのだ。
水谷川警視はすぐに刑事の顔に戻り、事務的に告げた。
「……煌良。本当にいいのか?」
本多刑事が、苦渋に満ちた声で娘に問いかけた。その手は、ストレッチャーの上の白布にかけられているが、まだめくろうとはしない。
「遺体は、土砂崩れに巻き込まれている。……正直に言うが、損傷が激しい。顔を見ても、お前が知っている美月さんだとは判別できないかもしれない。見るには、相当な覚悟がいる。……それでも、見るか?」
父親としての悲痛な警告。 煌良ちゃんは、血の気の引いた蒼白な顔で、それでも震える唇を噛み締め、小さく頷いた。
「……うん。確認する。……だって、美月じゃないかもしれないもの。私が、確かめる」
一縷の望みにすがるような、悲しい決意。 本多刑事は、覚悟を決めたように深く息を吸い込んだ。
「……わかった」
彼の手指に力がこもる。 ゆっくりと、残酷な真実を隠している白布が持ち上げられようとした、その時だった。
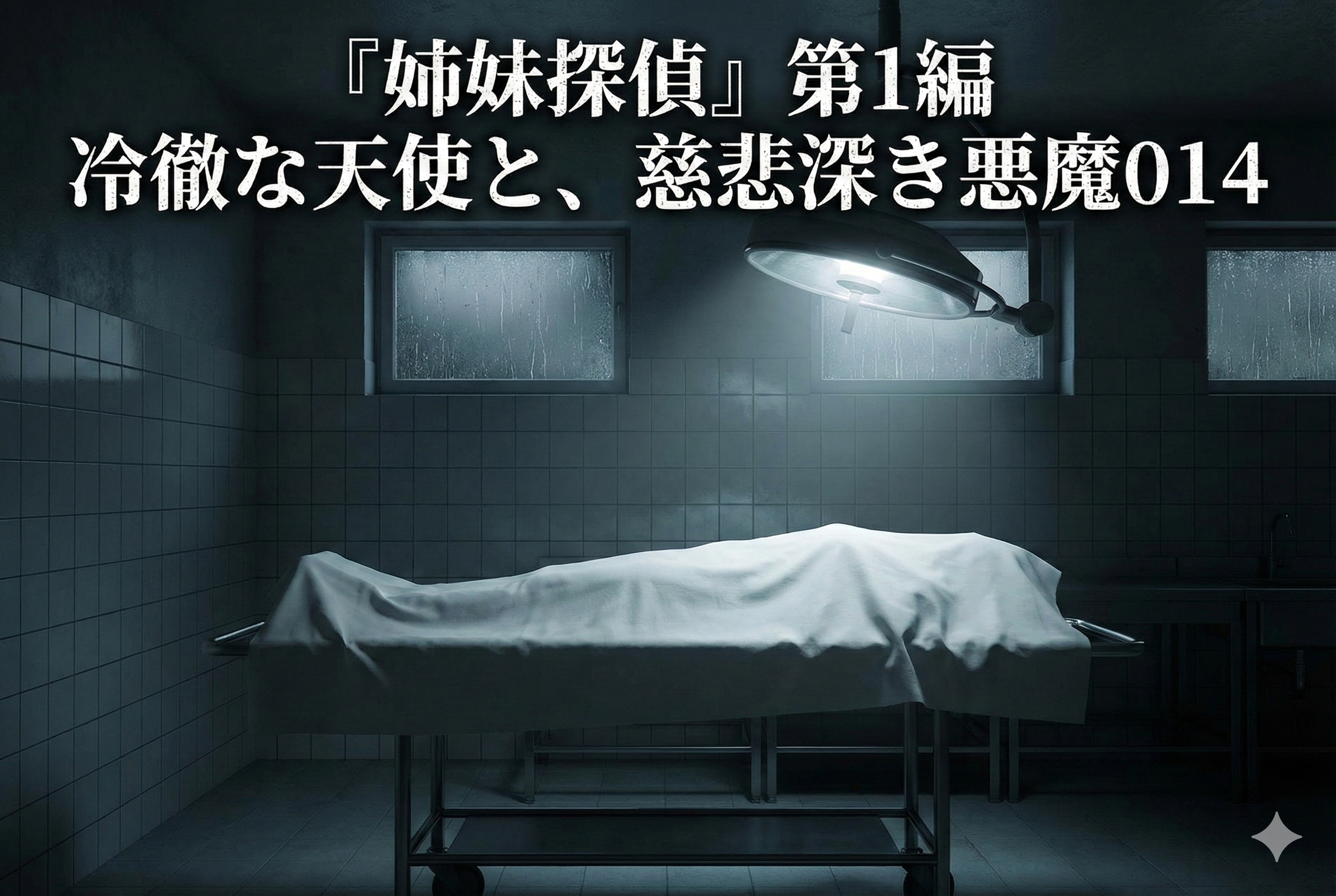


コメント