第二章 空白の三日間と雨の旋律
空白の三日間
3日後の午後2時。 店内に置かれたアンティーク時計の針が約束の時間を刻んでも、ドアベルの『ボーッ……』という音が響くことはなかった。
窓の外では、朝から降り続く冷たい雨が、アスファルトを黒く染めている。 店内に流れるクラシック音楽――サティの『ジムノペディ』が、雨音と混じり合い、やけに虚しく、そして不安を煽るように響いていた。
「……来ないね」
カウンターの中で、煌良ちゃんが何度もスマートフォンの画面を確認し、不安げに呟いた。その背中から滲み出る「焦燥」の波長が、私の肌をチリチリと刺す。
「連絡は?」
「つかない。既読にもならないの。こんなこと、美月には初めてで……」
姉はカウンターの隅で、分厚い洋書の文庫本を読みふけっていたが、ふと顔を上げた。その瞳には、すでに不穏な色が宿っている。ページを繰る手が止まり、パタン、と乾いた音を立てて本が閉じられた。
「……私の計算違い(ミス)ね」
姉が小さく、けれど重く呟いた。
「時差ボケの調整などと言わず、あの時すぐに会っていれば」
この3日間、姉は何をしていたか。決して遊んでいたわけではない。役所へ行って転入届や保険の手続きを済ませたり、イギリスで取得した運転免許を日本の免許に切り替えるために免許センターへ行ったりと、帰国後の事務処理を淡々と、しかし完璧にこなしていたのだ。 「生活の基盤(ベース)を整えてからでないと、良い仕事(パフォーマンス)はできない」。それが姉の論理だった。けれど、その「論理的に正しい順序」が、今回は裏目に出たのかもしれない。
「煌良。警察に連絡を入れなさい。ストーカー相談の実績があるなら、捜索願の受理は早いはずよ」
「えっ、でも、まだ約束の時間から30分しか……」
「『時間を贈られた』人間が、時間を破るはずがない」
その時、私は姉の言葉の真意を即座には理解できなかった。ただ、姉のその声は予言のように冷たく響き、決定的な不吉さを孕んでいたことだけは分かった。
犯人が被害者に「古びた物(時間の経過)」を贈っていたというプロファイル。その文脈において、被害者が時間のルールを破ることは、物語の「終わり」を意味するということなのだろうか? そんなこと、あってはならない。そう否定しようとするほどに、私の胸は正体不明の恐怖で締め付けられた。
「……行くわよ」
「え? どこへ?」
「決まっているでしょう。久世美月の自宅よ。ここで待っていても時間の浪費よ」
私たちは突然のことに戸惑いながらも、傘もささずただ、姉の後を追った。
自宅の駐車場へ着くと、そこには、灰色の雨に打たれながらも鮮烈な光を放つ、一台の車が停まっていた。
真っ赤なボディ。四角いフォルム。ダイハツ・タント。
昨日、納車されたばかりの新車だ。 姉がイギリスにいる間に、ネットの写真だけ見て、オンラインで商談し、帰国のタイミングに合わせて納車させていたものだ。実物も見ずに車を買うなんて、姉らしいと言えば姉らしいけれど。
「乗って」
姉がスマートキーでスライドドアを開ける。 運転席に乗り込んだ姉は、手慣れた様子でシートベルトを締めながら、ナビに久世美月さんの住所を入力し始めた。後部座席に煌良ちゃん、助手席に私が座る。
「それにしても、佳穂が軽自動車を選ぶなんて意外だったわ。もっとこう、イギリス帰りらしくミニクーパーとかに乗るのかと思ってた」
重苦しい空気を変えようとしたのか、煌良ちゃんが少し明るい声で言った。
「非合理的よ」
ハンドルを握りながら、姉が即答する。感情の色はない。
「日本の道路事情、特に都内の狭い路地において、軽自動車の規格は最強の『機動性(モビリティ)』を誇るわ。維持費、税金、燃費。どれをとってもコストパフォーマンスが最適解だもの」
「でも、赤色って派手じゃない? 佳穂の好みとも違う気がするけど」
「色彩心理学や好みで選んだわけじゃないわ。進出色(あか)は、人間の視覚において最も認識されやすい波長なの。他車からの視認性を高め、事故遭遇率を統計的に下げるための『安全対策(リスクヘッジ)』よ。……可愛さなんて考慮していない」
姉らしい。とことん理屈っぽい。でも、その赤いタントをクールな美女が真顔で運転しているという構図は、傍から見れば少し滑稽で、愛らしくもある。
ただ、今の姉の横顔に、余裕はなかった。 ハンドルを握る指が、白くなるほど強く食い込んでいる。無表情の仮面の下で、姉のプライドと後悔が、マグマのように静かに沸騰しているのを私は感じていた。
ワイパーが雨を弾く規則的な音だけが響く車内で、姉が唐突に尋ねた。
「煌良。その久世美月という友人は、どんな人間?」
「えっ? どんなって……」
「性格特性(パーソナリティ)の話よ。『警戒心(ヴィジランス)』は強い方? それとも……」
煌良ちゃんは少し考え込み、そして寂しげに微笑んだ。
「……優しい子よ。優しすぎるくらい」
「優しすぎる?」
「うん。例えばね、雨の日に捨て猫がいたら、自分が濡れてでも傘をさしてあげるような子。困っている人がいたら、放っておけないの。昔から、自分のことより他人のことを優先しちゃうところがあって……」
「『警戒心(ヴィジランス)』よりも、『共感性(エンパシー)』が勝るタイプ」
姉の目が、バックミラー越しに鋭く細められた。その瞳の奥で、カチリ、と何かが噛み合う音がした気がした。
「……『最悪の相性(ワースト・マッチ)』」
「え?」
「彼女のようなタイプは、『捕食者(プレデター)』にとって最高の『獲物(プレイ)』になる。善意という名の隙(スキ)があるから」
姉の冷徹な分析に、車内の空気がさらに冷え込んだ気がした。優しさが仇になる。人を思う心が、死を招く引き金になる。そんな理不尽なことがあっていいのだろうか。
重苦しい沈黙が流れる中、後部座席の煌良ちゃんが、震える声で尋ねた。
「ねえ、佳穂。……さっき言ってた、『時間を贈られた人間が、時間を破るはずがない』って……あれは、どういうこと?」
店を出る直前に姉が口にした、予言めいた言葉。それがずっと、彼女の喉に棘のように刺さっていたのだ。
姉はバックミラー越しに煌良ちゃんへと視線を向け、静かに問い返した。
「煌良。確認させて。……久世美月という女性は、時間にルーズな人間? それとも、約束の時間(タイムリミット)をきっちり守るタイプ?」
「……ええ。絶対に遅刻なんてしないわ。待ち合わせには必ず5分前には来てるような子だよ。時間を……約束を大切にする子だから」
煌良ちゃんの答えを聞いて、姉は小さく頷いた。その表情には、パズルのピースが嵌まった時のような、冷ややかな納得の色が浮かんでいた。
「やっぱりね。……犯人が被害者に『古びた物(時間の経過)』を贈っていたことから推測したのだけれど、プロファイルは合致していたわ」
姉は前を見据えたまま、淡々と告げる。
「犯人は、彼女のその『律儀さ』を見抜いていた。時間を守る彼女だからこそ、時間を象徴する物を贈り、執着した。……だからこそ、彼女が自らの意志で時間を破ることはあり得ない。彼女が来なかったということは、物理的に来られない状況――つまり、被害者はすでに……」
「佳穂ッ!!」
煌良ちゃんが悲鳴のような声を上げた。
「……被害者とか、言わないで。美月はまだ……!」
バックミラーに映る煌良ちゃんの顔は蒼白で、恐怖に小刻みに震えていた。姉の論理は正しい。けれど、その正しさは今、親友を想う煌良ちゃんの心を鋭利な刃物で抉る凶器にしかならない。
姉はハッとして口をつぐみ、握りしめていたハンドルを僅かに緩めた。
「……ごめん」
短く、小さな謝罪。 姉はそれ以上何も言わず、ただアクセルを深く踏み込んだ。言葉で取り繕うよりも、1秒でも早く現地へ辿り着くことこそが、今の自分にできる唯一の誠意だと示すように。
車は雨飛沫(しぶき)を上げ、久世美月さんのマンションへと急いだ。 ワイパーが忙しなく動き、叩きつける雨粒を拭い去っていく。車内には、エンジン音と雨音だけが満ちていた。
私は、ハンドルを握る姉の横顔を盗み見た。無表情に見えるその瞳の奥には、自分自身の論理が親友を傷つけてしまったことへの、静かな痛みが滲んでいるように見えた。
「ごめん」
さっき、姉が煌良ちゃんに言った、短く小さな謝罪。それが私の耳に、いつまでも残っていた。 姉が誰かに謝ることは、滅多にない。それは姉が傲慢だからではない。彼女の行動や発言は常に論理的裏付けがあり、事実(ファクト)に基づいているからだ。「正論」を述べているだけであり、間違ったことはしていない。だから、謝る必要がないのだ。
けれど、煌良ちゃんに対してだけは違う。
(……煌良ちゃんは、特別なんだ)
助手席で揺られながら、私の記憶はふと、遠い過去へと引き戻された。まだ、両親が生きていて、私たちが幼かった頃の記憶へ。
子供という生き物は、純粋ゆえに残酷だ。 異質なものを本能的に嗅ぎ分け、徹底的に排除しようとする。
姉がまだ、小学校の低学年だった頃のことだ。
IQ240の頭脳を持つ姉にとって、小学校の授業など退屈な時間でしかなかっただろう。テストは開始数分で全問正解し、余った時間で教師すら読めないような専門書を読み耽る。話し方も、当時から今のままだった。先生の板書の間違いを指摘し、同級生の非論理的な言い訳を、「それは矛盾している」と冷徹に論破する。
当時の子供たちにとって、「天才」という概念は理解の範疇を超えていた。理解できないものは「異端」であり、「恐怖」の対象となる。
『あいつ、変だよな』 『なんか、ロボットみたいで気持ち悪い』 『宇宙人なんじゃない?』
男子たちは遠巻きに姉を指差し、嘲笑った。女子たちはヒソヒソと陰口を叩き、姉をグループから排除した。 姉は、そんな周囲の反応を意に介さないフリをしていたけれど、休み時間に一人、教室の隅で本を読んでいる姿は、幼い私の目にも痛々しいほど孤独に映った。
けれど――そんな灰色の世界に、たった一人だけ、鮮やかな色彩を持った少女がいた。
『ねえ、佳穂ちゃん。何読んでるの?』
本多煌良ちゃんだけは、違った。 彼女だけは、周りの空気を読むことなく、ごく自然に、当たり前のように姉の隣に座った。 「変人」としてではなく、「佳穂ちゃん」として接してくれた。
当時、私はまだ幼稚園に入ったばかりの幼児だったけれど、小学校の行事や、家が近所だったこともあり、その光景をなんとなく覚えている。
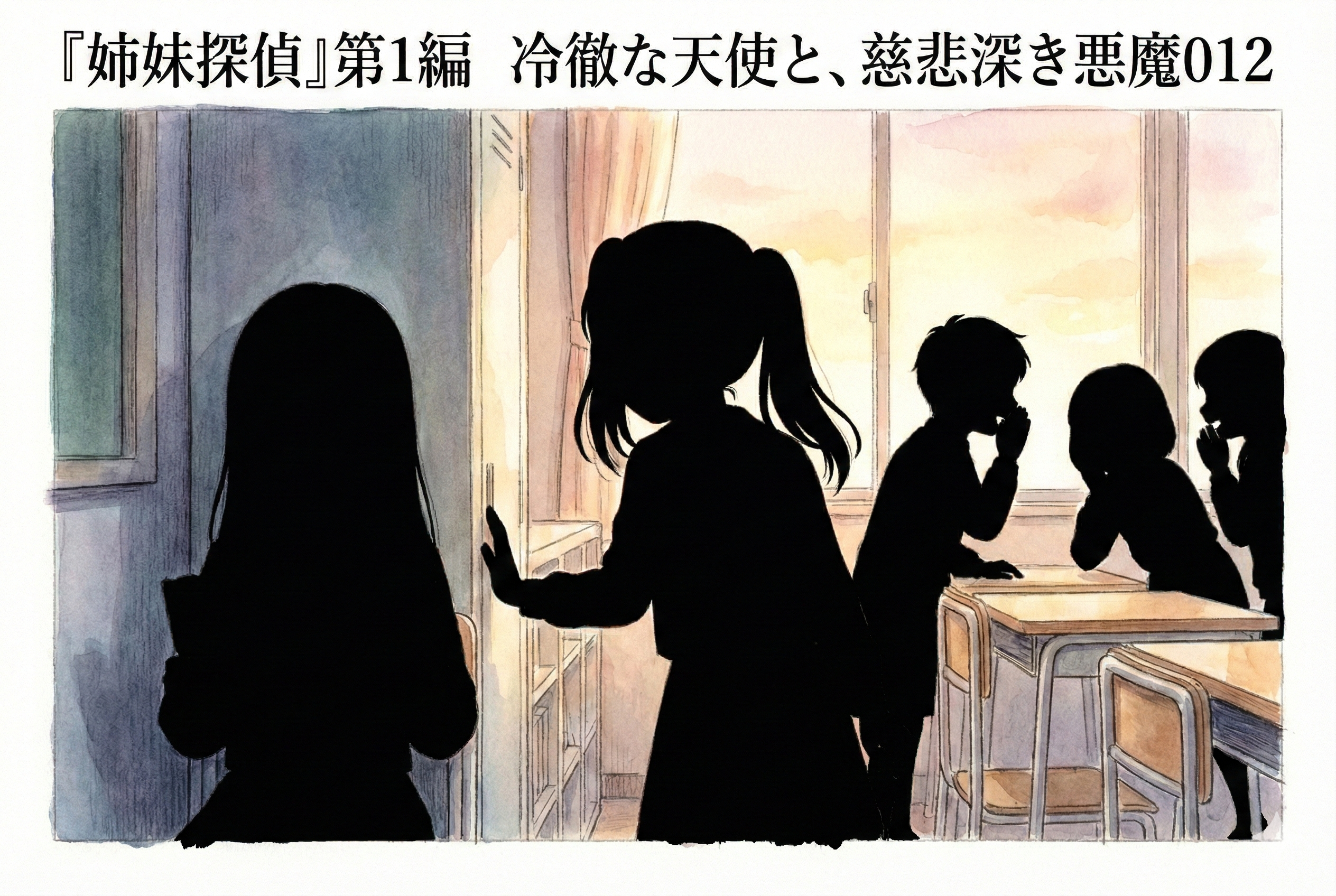


コメント